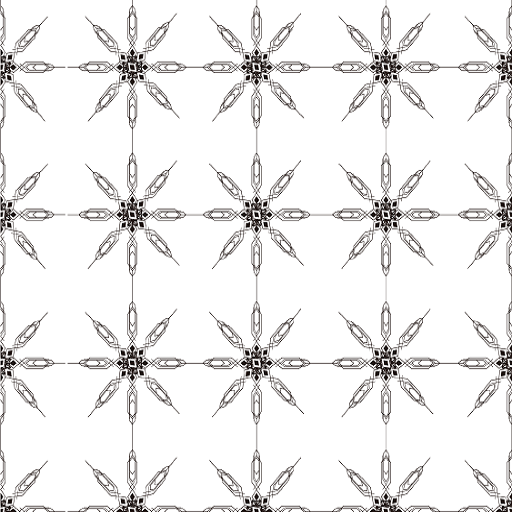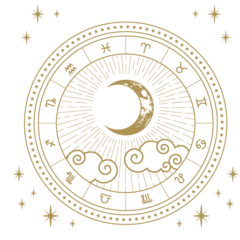親からの心理的な支配を理解しようと、人生の半分をセラピーに費やしているクライアントがいた。でも彼らはそのコードを、けっして完全には断ち切らなかった。三十代、四十代、あるいはそれ以上になって、過去の惨めな奴隷でいる人ほど痛ましいものはない。私自身の父はとても寛大な心と、抜群のユーモア感覚を持っていたが、私の幼い頃はかなり要求の厳しい人でもあった。彼にとっては、何も充分良いと感じられなかった。ある種のカルマを解消すべく、私が魂としての彼を選んだとは思う。しかし私はおとなになっても、彼の絶え間ない批判の声みたいなものから自分自身を解放しきれないでいた。父のことは深く愛していたが、私の一部は、従順でがっかりさせてばかりの子どものままだった。数か月前、私はひどい執筆スランプにぶちあたった。締め切り直前の企画もひとつあった。そこである日、私は必死に祈った。「お願いです。私をここから出してください。私は自分自身の声が必要です。このままの私で充分である必要があります」 気がつくと、海に引かれている感じがした。知ってか知らずか私を傷つけた父からの手紙を持って、私は海に向かった。正直なところ、もはや何が現実で何が自分自身のこりかたまった反応なのか、わからなくなっていた。それから私は、ココナッツと花を買いに店に立ち寄った。以前に別のことでおこなった、インドの儀式をするつもりだった。このごちゃごちゃの一切を、これを最後に神に捧げるときがきていた。私はじっくりと時間をかけて瞑想し、膝の上に置いたココナッツに、満たされない思いや感覚をすべて入れていった。それから立ち上がり、石の壁めがけてそれを思いきり投げつけ、サイキック手榴弾のごとくミルクが爆発するのを見た。次は手紙を燃やさなくてはいけなかったが、風が強すぎて、ライターが使いものにならなかった。すると信じられないことに、数ヤード先でふたりの若い男性が大きな焚き火をしているのが見えた。「夢を見ているのかしら」私は思った。「真昼の海岸で?」 そこに歩み寄り、事の次第を説明した。ひとりが、「気をつけて! 猛烈に熱いから」と、注意をうながした。「あなたが火傷をしないよう、僕が投げ入れようか?」 「いいえ!」私は大声をあげ、風が髪を激しく吹きつけた。「私が娘だから。私がしないと!」 長い棒をつかんで、燃え盛るオレンジ色の炎に手紙を押しこんだ。紙が燃えてグレーの灰になって浮かんでくると、彼らは私にハイタッチをし、「自由になった、あなたは自由だ!」と大声をあげた。彼らのハイネケン・ビールで乾杯し、ひとりはちょっとした勝利のダンスまで踊ってくれた。それから私は感謝をこめて、気性の荒い最愛の父にとりわけ感謝しながら、紫の蘭を波打ち際に並べた。私の激しくて情熱的な奔放さは、まさに父譲りだった。わかるかと思うが、内にいる人質は、あなたがどこかの時点で解放してやらなくてはならない。その門を突破してくれる人は、あなた以外に誰もいない。 あなただけが、最終的にバリケードを破って自由にしてやれるのだ……あなた自身を。
インナーチャイルドの癒やし
Categories: